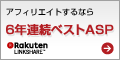「IT業界を去ろう」--そう思った時に見直すべき10項目
Jack Wallen氏は以前「IT業界の仕事を辞めたくなるとき--10の理由を紹介」という記事で、IT業界を離れたくなる理由をいくつかリストアップした。今回わたしはこの記事で、Wallen氏とは異なる観点でIT業界にとどまるべき理由を紹介したい。
1.カネ
お金を稼ぐために仕事が大変なのは確かだが、ITプロフェッショナルにはその大変な仕事に見合うだけの稼ぎがある。その給料は単に「いい」という程度ではなく、ずば抜けている。米労働統計局が発表した、「An Overview of U.S. Occupational Employment and Wages in 2010(PDF:米職業別雇用状況と賃金)」(Chart 6)によれば、コンピュータおよび数学関連の職業は平均年収が7万7230ドルであり、2010年の主な職種グループの中で3位を占めている。これよりも年収が高いのは、経営職と法曹職だけだ。
2.プロフェッショナル性
もし読者がわたしと同じような環境で仕事をしているのなら、誰と働くかは非常に重要なはずだ。とにかく、あなたの仕事人生の4分の1以上は、そういう人たちと過ごすことになる。わたしはプロフェッショナルな人とも仕事をしたし、そうでない人とも仕事をした。わたしは前者が好きで、後者は避けている。わたしは、例えば軍需産業などほかの職業のプロフェッショナルにも会ったことがあるが、IT業界の人たちのプロ意識はずば抜けている。
3.キャリアの連続性
2回目にIT業界を離れたとき、わたしは何もせずにしばらく休みを取りたかった。その後、一旦キャリアから離れてしまうと復帰がどんどん難しくなることを悟ったが、後の祭りだった。最大の問題は、潜在的な雇い主からどう見られるかということだ。雇う側は、履歴書に穴が空いているのを好まない。仕事を辞めれば、無職でいることが差別対象となるのは本当だということを、わざわざ厳しい方法で学ぶ羽目に陥りかねない。
4.挑戦
わたしがプログラムを書く職業を選んだ理由の1つは、それが挑戦的なことだと感じたからだ。コーディングをしていると、行く手に障害が現れない日は1日もない。ITプロフェッショナルは、パズルや問題解決を生き甲斐にしている。正しい心がけをしていれば(この心がけはIT業界で成功するには必要なことだ)、障害は挑戦になる。情報技術は難しいが、退屈を感じることはないはずだ。IT業界での役割がなんであれ、そこで明日ぶち当たる障害は、今日経験したものとは違うものである可能性が高い。
5.報酬
挑戦はそれ自体が報酬である。これがIT業界を選び、そこにとどまるもう1つの理由だ。わたしは、自分が書いたプログラムが実際に設計した通りエラーを出すことなく動作したり、大型のシステムプロジェクトが期日通りにきちんと終わった時ほどプロフェッショナルとして満足感を味わうことはない。それで誰かの命が救われるわけではないかもしれないが、医療関係の仕事をサポートすれば命を救う役に立ったことになる。また、機械にできて機械に任せるべき仕事から、肉体労働者や頭脳労働者を救うことができる。わたしがこれまでに作ったシステムは、多くのくだらない仕事を肩代わりするものだった。時々経験する修羅場を除けば、わたしは1週間の終わりには、他人の仕事を支援できたと感じ、心の底から満ち足りた気分になる。IT業界のどんな役割であっても、人々や仕事の支援につながっており、そこで感じる自尊心や達成感は大きな見返りだ。
TechRepublicのメンバー、Chronological氏は、「IT業界での仕事は、もしかすると最も挑戦的な仕事かもしれない。最も豊かな仕事ができる業界であることは100%確実だ」と表現している。
6.市場競争力
ITプロフェッショナルは、職探しや職の維持に成功する可能性が高い。ITプロフェッショナルの将来は(少なくとも米国においては)明るく見える。CNN MoneyとPayScaleがランク付けした成長潜在力のある給与水準の高い職トップ20のうち5つ、トップ50のうち14がIT関連の職業だ。
7.スキル
IT業界で働きたいという人は、一般的に極めて知的であり、独特の特性とスキルを持っている。またIT業界は、分析的に考え、技術に傾倒している人材を惹きつける。もし読者がこのような資質とスキルを持ち合わせているなら、IT業界に居場所を見つけられるだろう。
IT業界にとどまるべきもう1つの理由は、スキルを最先端に保てるということだ。IT業界を長く離れすぎると、スキルはさび付き、時代遅れにさえなることもある。IT業界を離れる前に、現在の雇い主が自分に新しいスキルを学ばせてくれ、現在持っているスキルを最新の状態に保たせてくれているということを考慮すること。こうしたスキルは、自分の将来に対する投資だ。
8.尊敬
Wallen氏は自分の記事の中で、ITプロフェッショナルは一般人から尊敬を得られないと述べていた。フォーラムのコメントでも、読者の多くがこれに賛同し、本来ふさわしい評判や尊敬が得られていないと書いていた。もし十分にいい仕事をしていてもそうなのであれば、尊敬を得られないのは相手の無知のせいであって、自分の落ち度ではないかもしれない。
一般の人から敬意を受けるのは難しいかもしれないが、同僚から敬意を払ってもらうことはできる。知識のある賢いプロフェッショナルは、他人の貢献を評価し、相手に対して敬意を示す。IT業界は、敬意を受けるには格好の場所だ。IT業界で尊敬を受けられないとすれば、おそらくほかのどの職業でも無理だろう。
わたしは単に運がいいか単純すぎるのかもしれないが、わたしはこれまでいつも上司や同僚、顧客から敬意を払ってもらってきたと考えている。より重要なのは、敬意というのは考え方の問題であり、他人が自分をどう見ているかということに対する自分の態度や見方の方なのかも
9.ギーク心
IT業界は、自らの最新技術への欲求を満たすのに完璧な場所だ。自分のギーク心を満たしつつ、給料を払ってもらえる場所がほかにあるだろうか。もしバイトやギガヘルツ、フローチャート、If...Then...Elseステートメントといったことを考えるのが好きなら、興味や独特の言葉を共有している人たちと一緒に働くのは楽しいはずだ。
10.ITへの愛
IT業界で働くことを選んだ人のほとんどは、自分のやっていることを愛している。読者も認めざるを得ないだろう。心の奥底では、自分の仕事を愛しているはずだ。そうでない人にとっては、すべては相対的な問題だろう。ほかの普通の人が就く仕事やその給料を考えれば、IT業界が好きになれるはずだ。もしITの仕事に対して何も感じないのであれば、ひょっとすると別の道を考えるべき時かもしれない。
ある掲示板におけるIT_Goddess氏の発言が、一番うまく状況を表現していると言えるだろう。「本当に自分の仕事を好きだとか、愛していると言える人は多くない。だからIT業界の外では、多くの人がいやいや仕事に行っている。しかし、わたしが知っているIT業界人のほとんどは、自分の仕事を愛している。仕事に見合う給料がそれなりにもらえていればの話だが」(IT_Goddess氏)
結論
わたしは「正式」なIT業界からは長い間遠ざかっているが、これまでの苦い経験を通じてこの業界にとどまるべき多くの理由を学んだ。白状すると、わたしはここに挙げた項目の順に、多かれ少なかれミスを犯した。IT業界で働く根本的な理由は、IT業界はほかのどの職業よりもテクノロジ好きのニーズを満たしてくれるということだ。そして、この仕事はいい仕事だ。The Wall Street Journalによれば、2011年のいい仕事トップ5のうち2つはIT関連の仕事(ソフトウェアエンジニアとシステムアナリスト)だ。
来る日も来る日も責任を負い続けるストレスを抱え、長時間くたびれるまで働き、数多くの終わらないフラストレーションを持つ毎日のつらさは、わたしもよく理解している。やるべきことをひとつずつこなし、1通ずつメールに返事を書くことばかりに集中していると、木を見て森を見ることができない状況にもなる。自分の今いる環境のプラスの側面が見えなくなるのは人間の性なのだろう。Joni Mitchell氏は、次のように歌っている。「Don't it always seem to go that you don't know what you've got 'til it's gone.(なくしてしまうまで自分が持っているもののことはわからない。そんなものでしょう?)」IT業界の数多くの恩恵を理解するために、わたしがそうしたように、わざわざIT業界を離れる必要はないはずだ。
出展
http://japan.cnet.com/sp/businesslife/35005121/